
|
|
音円盤アーカイブス(05年12月06年1月) NOAH BAERMANはEHLERS-DANLOS SYNDOROMEという病気を持っている。 ネットで検索して調べてみたけど、大変そうな病気である。 患の特徴 Ehlers- Danlos 症候群、血管型(EDS4としても知られている)は薄く透けて見える皮膚、易出血性、特徴的顔貌、動脈・腸管・子宮の脆弱性に特徴付けられる。罹患者は動脈破裂、動脈瘤、動脈解離、胃腸穿孔・破裂、妊娠中の子宮破裂のリスクを有する。20歳までに1/4の患者が、40歳までに80%の患者が何らかの明らかな医学的問題を経験する。 著者: Malanie G Pepin, MS; Peter H Byers, MD 日本語訳者:古庄知己(信州大学医学部附属病院遺伝子診療部)より引用 この作品はEDSの専門機関EHLERS-DANLOS NATIONAL FOUNDATION及びEDS患者の為にNOAHが録音した作品で、アルバムの収益は全額、EDNFに渡されるようだ。 販売もEDNFにしか在庫をおいていないようで道理で市場に出回らないはずである。 そしてこのCD,メンバーがロン・カーター、ベン・ライリー巨匠二人を招いてのスペシャルトリオなのであります。 最も、出来上がった作品がしょぼかったらお話にならないのですが、これが素晴らしい出来なのです。 さすがはベテラン2人、NOAHの意向を見事に汲み取り素晴らしい協調性を見せる。 そこに勿論自身の主張を盛り込む事に抜かりはない。 NOAHも最高のリズム隊にサポートされて雲の上の絨毯にでも乗っている心地だったに違いない。 一番のお薦め曲は「PATCH KIT」。 そこはかとない哀愁が滲み出た飽きの来ない良曲だと思う。 「JAZZ BAR 2006」にいれてほしいような曲。 メンバーはNOAH BAERMAN(P)RON CARTER(B)BEN RILEY(DS) 録音は2002年9月12日 SYSTEM TWO STUDIOS BROOKLYN , NY -----------  現在NYで活躍するピアニスト、DEANNA WITKOWSKIの2003年作。 ここ最近めきめき調子を上げているテナーのDONNY McCASLINを従えてのカルテットの編成となっている。 つい最近ARTIST SHAREから最新作をリリースしたところで、そのアルバムも今度入手したいと思っています。 90年代にアフロキュバーンリズムやチョチョ・バルデスのようなキューバンピアノの研究を相当したらしい。 彼女の作曲にリズムの構成面やピアノ奏法に影響を及ぼしている事は確かで、ユニークだ。 ブルージーな要素はあまり見当たらないが歯切れがよくタッチの美しいピアノで、彼女の音楽はクラッシックとジャズとアフロ音楽がミックスされた独特のものでオリジナル性を感じる。 McCASLINをはじめとしてリズムセクションの好演も聞き逃せないと思う。 只、まだ、未消化のとこがところどころ見受けられるというか、音楽の初めから終わりまでしっかりとリスナーを引っ張っていく求心性に弱い面も見受けられる。 このアルバムではオリジナルとスタンダードを半々の比率くらいで演奏している。 スタンダードではどちらかというとピアノプレイに焦点が当たっているのに対し、オリジナルではサウンド指向の面が強いのだけれど、どちらもがまだまだ発展途上の段階だと思うのだ。 ポテンシャルを感じるアーティストなので、どちらの方にフォーカスしていくかで今後の展開も見えてくると思うし、どちらに転んだとしても期待できる音楽家だと思う。 メンバーはDEANNA WITKOWSKI(P)DONNY McCASLIN(TS,SS)JONATHAN PAUL(B)TOM HIPSKINO(DS) 録音は2000年8月、2001年6月 ---------  このCDのインナースリーブの内側にティーンエイジのMARK COLBYとスタン・ゲッツが一緒に写っている写真が載っている。 COLBYが、アイドル、憧れの存在、音楽的影響を最も受けた心の師であるスタン・ゲッツに全面的にトリビュートした作品です。 子供の頃、姉のロザリーがジャズサンバに収録されている45回転のEP盤の「デサフィナード」をかけたことでCOLBYの人生が変わったという。 MARK COLBYと言えば、タッパンジージーレーベルのフュージョンサックス奏者のイメージが強かったのでありますが、数年前にリリースされたデュオ作など、本来は根っからのジャズミュージシャンだったようだ。 その点、アーニー・ワッツと同じ様な境遇だと思うが、COLBYの方がジャズ度が高い。 スタンに対する尊敬の念に留まらず、長い間夢に思い続けてきたプロジェクトだけに、隅々まで行き届いたアレンジメントがなされている。 それが演奏をより助長する役割を担っておりとても自然な編曲となっていることを評価したい。 ゲッツがらみの楽曲の素材のよさはあるにしても、ここでCOLBYはスタンに負けないくらい歌心に溢れた素晴らしいサックスを全編に渡って披露している。 ブラインドで聴けば、VERVE後期のアルバムと間違うのではないかと思ってしまうほどだ。 スタンのサックスにそっくりではないかという声もあがろう。本人もそう言われれば嬉しいに違いない。 ここでそう言う事は褒め言葉になると思うのだ。 メンバーはMARK COLBY(TS)JIM McNEELY(P)KELLY STILL(B)JOEL SPENCER(DS) DICK SISTI(VIB)ERIC HOCHBERG(B)BOB RUMMAGE(DS)その他ストリングス、オーケストラ ----------  ほんと、アルバムタイトル通り、トゥウィンクルっていう感じなのである。 とくに1曲目。「WATASHI’」。 日本語で唄っている。その事自体別に珍しい事ではないかも知れないけれども、唄の弾み具合がとてもいいのであります。 こちらまでウキウキした気分になってくる。 透きとったクリスタルなヴォイスで軽やかに弾む歌唱はジャズボーカルで珍しい部類に入るかもしれないけれども、とても自然でいい感じなのである。 ピアノトリオ作品が好評だったNICO MORELLIがピアノを弾いていて、ここでも素晴らしい伴奏振りを披露している。 アルバムの選曲はバラエティーに富んでいて、1曲目軽やかなサンバ調、ジャズスタンダード、クラシカルでフォーキーなバラード、アカペラ、スキャット、などが楽しめて飽きさせない。 パット・メセニーの「JAMES」も軽やかで悪くない。 「I COULD WRITE A BOOK」や「THEY CAN'T TAKE THAT AWAY FROM ME」スタンダードを唄っても彼女のオリジナル性を感じさせる歌唱で、聴かせるものを持っている。 女性ボーカルファンには是非聴いてもらいたい作品です。 メンバーはVICTORIA RUMMLER(VO)NICO MORELLI(P)YORGOS DIMTRIADIS(PER)GIANNI GUIDO(G)THIERRY COLSON(B)GUILLAUME KERVEL(STEEL DRUM) -----------  ペレスにはダニロ以外にもう一人異才がいた。 そのもう一人のOSCAR PEREZはNYで活躍するピアニストで、実際ダニロ・ペレスは師匠に当たるようだ。 この作品は彼のクインテットにWYCLIFFE GORDONとPETER BERNSTEINがゲスト参加したもので、2005年に自費制作でリリースされた。 自身の音楽的ルーツであるキューバ音楽をうまくジャズに取り入れた作曲はとてもユニークであり、魅力的だ。 もちろん、土着のラテン性は薄めれれて洗練されたスタイルに再構築されているわけなのだけど楽曲に血が通っていてフューチャーされるソロイストが生きる楽曲づくりがなされている。 OSCAR自身のピアノはもちろんのこと、バンド全員の活気溢れたソロ・アンド・アンサンブルも聴きもの。 ゲスト参加のWYCLIFFE GORDONとPETER BERSTEINもいいソロをとっている。 まだまだ無名だけど今後に期待したいピアニストの登場だと思う。 メンバーはOSCAR PEREZ(P,FENDER RHODES)GREG GLASSMAN(TP,FLH)STACY DILLARD(SAX)ANTHONY PEREZ(B)EOFF CLAPP(DS)ANGEL DESAI(VO)EMILLNO VALERIO(PER)WYCLIFFE GORDON(TB)PETER BERNSTEIN(G) 録音は2005年7月28日 NYC ---------  カナダ、バンクーバーで活躍する歌手LEORA CASHEの2005年作。すでにアルバムは何枚かリリースしているがこの作品がジャズ歌手としてのデビュー作のようだ。 前作はゴスペルの作品だったようだ。 ゴスペルシンガーというと、声量豊かにシャウトするスタイルが想像されがちだけど、もちろんそれオンリーではなくて、歌に対するダイナミクスが必要とされるだけあって、繊細な表現も問題ない。 ゴスペルフィーリングが鼻につくこともなく、素直でストレートな感情表現が好ましい。 声量が結構あるようなので、常に余裕を持って歌っているので危なげなく安心して彼女の唄に身をまかすことができるのだ。 だからといって、ジャズ的スリルに乏しいわけではなくて100%全力投球の姿勢がうかがえて好感を抱く。 バックもソリッドで手堅いピアノトリオなので、ジャズクラブの前の方の席で聞いている様な気分を味わえること受け合い。 「LONG AGO AND FAR AWAY」「OLD DEVIL MOON」「LOVER COME BACK TO ME」「DO NOTHING TILL YOU HEAR FROM ME」「MY HEART STOOD STILL'」「MIDNIGHT SUN」「COTTONTAIL」「BLUE SKIES」「LOVE ME OR LEAVE ME」 など、緩急自在な選曲で飽きさせない。 メンバーはLEORA CASHE(VO)RUSS BOTTEN(B)TONY FOSTER(P)JON WIKAN(DS)CRAIG SCOTT(DS)ROSS TAGART(P)MILES FOXX-HILL(B) 2005年作品 ----------  JOHN STETCHの1994年作品。 JUSTIN TIMEからのピアノトリオのヒット作以降名前が知れ渡ったけれども、この作品がリリースされた当時は知る人ぞ知る存在だったはず。 私も当時は知りませんでした。 サイドマンのSEAMAS BLAKEやJORDI ROSSY,UGONNA OKEGWO,GENE JACKSONの方が有名だったのは確かだろう。 とここまで書いて、ふと窓の外の景色を見る。 先々週からの寒波の影響の雪もだいぶ溶けて山間がやけに近くに見える。 外の空気は今日も冷たいが朝から晴れ渡ったよい天気で気持ちよい。 冬のやわらかい日差しが早くも春の訪れを予感させるような・・・ JOHN STETCHのピアノはこの作品であたかも冬の日差しのように柔らかく繊細な光の粒子を運んでくれる。夏の強く照りつけるような力強さはないのだけれど、周りの風景をくっきりと浮かび上がらせ、空気を澄み渡らせるような長い波長の日の光。 冬の晴れ渡った公園のベンチや芝生で過ごしているといつのまにか、身も心も穏やかで温かい気分になるのと同じように、この作品はダイレクトにきいてくるインパクトや即効性はないのだけれど、じわじわとその良さに魅了されてくるのです。 最初はやや遠慮がちとも思われる繊細な雰囲気が、温度感の上昇とともに、周りの風景がよく見えてきてプレイヤー間の連携プレイにすっかり魅了されている自分がいるというわけ。 SEAMUS BLAKEのサックスもすでに個性を感じさせる良いプレイです。 現代のジャズシーンを10年以上前から見据えていたかのような音つくりは今の耳で聴いても新鮮だ。 メンバーはJOHN STETCH(P)SEAMUS BLAKE(TS)JESSE MURPHY(B)JORDI ROSSY (DS)UGONNA OKEGWA(B)GENE JACKSON(DS) 録音は1993年11月8,9日 BROOKLYN, NY -------------  SCHEMAから2000年にリリースされたクラブシーンを意識したイタリアンハードバップの力作。 一年の終わりをこういう元気のある痛快エンターテイメントハードバップを聴いて締めくくることにしよう。 ROSARIO GIULIANI,FABRIZIO BOSSO,GIANLUCA PETRELLA,PIETRO LUSSU,GIUSEPPE BASSI,LORENZO TUCCI、現在イタリアジャズを聴いている人には今やお馴染みの綺羅星のようなメンバーが勢ぞろいしている。 2000年当時(録音は1999年)は知っている人があまりいなかったことが想像に難くない。 ニコラ・コンテのしたたかな計算によってプロデュースされたとびきりカッコいいジャズという作為性が見え隠れしないことはないのだけれども、正統派ジャズおやじが聴いても、十分納得できる作品の完成度とジャズスピリットを持ち合わせている作品だと思う。 ベースになっているのはBASSO=VALDAMBRINIクインテットなのは楽曲を含めて間違いないのだがそこは現代イタリア若者によるジャズ。 タイム感覚やスピード感が現代仕様にチューンナップされていると感じるのは私だけだろうか? とにかく聴いていて痛快、これを聴いている間は嫌な事も忘れてしまうこと受けあい。 カラッとした能天気なラテン民族特有の陽気さと50年代から60年代のジャズ特有の不良性、ノワール性がうまい具合でブレンドされたさじ加減も絶妙なものがある。 BOSSO,GIULIANIはじめメンバーの達者な表現力にも舌をまく。 皆、滅茶苦茶うまいのである。 現代イタリアジャズの成熟を表す第一歩のような作品だと思うのだけどどうだろう? 録音は1999年12月6,7,8日 ----------  新年おめでとうございます。 本年も宜しくお願いいたします。 このブログサイトは2004年7月17日の開設以来、約1年半を迎えようとしているのですが、昨年の春くらいからご訪問 いただける方が増えてきて励みになりました。 感謝いたします。 そうですねぇ、とりあえず1年の目標としては、現在約150アクセス/日なのを200アクセス/日くらいまで増えてくれば嬉しいのですが・・・ JAZZのサイトではなかなか厳しいものがあるかもしれません。 もちろんアクセス数でなくて、ご覧いただいて何かを感じ取ってもらったり、そのミュージシャンに関心を持ってもらったり、CDを買ってもらうことが一番充実感を覚えるのですが。 ましてや、私のサイトは世界各国の現代ジャズを浮き彫りにすることに一番のポイントを置いているので、一般的なジャズファンの方はあまり関心が湧かないCDが題材になっていることが多いかもしれません。 たぶん知っている名前が少ないだろうと思います。 取り上げたCDの半分以上知っているあなたは、立派なジャズマニアだと思いますよ! それにもめげず今年もがんがん多種多様なジャズを取り上げていきますので宜しくお願いいたします。 まだまだ取り上げたいミュージシャンやCDが山のようにあるし、新譜CDも世界各国からリリースされ続けるのだ。 立ち止まってる場合ではない。 ゆっくりしたいとか、聴くべきCDがあまりないとか言っていえる場合ではない。 そういう人はそこで停滞していると言ってよい。その人のジャズはそこで終わり。 あとは反復、確認作業、ノスタルジアの世界の住人となるわけだ。 もちろん趣味の世界のことだから全然かまわないのですけどね。 あくまでも私一個人としてのスタンスを説明しているに過ぎません。 誤解なきよう。 スタイルや新しさだけを追い続けるわけではないのは当然として、ひとつこだわっていることがある。作為性のあるジャズ(いわゆる一部の日本のレコード会社に多い加工臭が鼻につきすぎる作品、日本人プロデュースによる日本人の為の日本人仕様のジャズ)は基本的に取り上げない。 で、そういう作品ほどよく売れているのは紛れのない事実だけれども(もちろん大量の販促費が投入されているのは言うまでもない。) 売れるのは全然かまわないのだけれどそういう作品が、マイルスの作品のようにクールではないのが残念なのだ。 年明け早々なんか頑固爺のような辛口批評のようになってしまいましたが、基本的に許容度の広い音楽嗜好をもっていますので、ここは聞き逃してください。 今年最初の一枚はこれにします。 PAULA SHOCRON/LA VOZ QUE TE LLEVA BLUE ART RECORDSから2005年にリリースされたアルゼンチンの女性ソロピアノ作品。 普通、ピアノソロは聴かないし、苦手。持っているソロピアノ作品と言えば、モンクが2枚、キース1枚(メロディー何とかって言う病気のリハビリ集みたいなCD)スティーブ・キューン1枚、それぐらいか? とにかくほとんど持っていないし関心外のジャンルなんでたいしたこと言えないのですがこれはレーベルサイトで試聴していっぺんに気に入りました。 光と影を感じさせる色彩感豊かな風のようなピアノと言えばよいかな? 柔らかいハーモニーとハードでストイックな表現の混ざり具合も面白く、 ジャズの語法を意識させない奏法もオリジナルなものを感じさせると思う。 オリジナルとモンクの曲を3曲。 録音は2005年 1,2ヶ月に一回ぐらいこんな減らず口をたたくと思いますがお許しを・・・ たまにはガス抜きしないとストレスたまっちゃうもんで・・・ -----------  今日は家族と昼から街中へ出かけた。 ちょうどシャレオ地下で中古市が開催されていたのでいつもの如く、どれどれといった感じでレコ掘り作業(CDか)を開始したのだけれど今一これというブツがない。 なにかひとつこれといったものがあれば、エンジンがかかってあれもこれもとなるのだけどこの日は不調に終わり結局なにも買わずじまい。 ついでにその足でTOWER RECORDへ行き、ジャズコーナーは今回は素通りして(年末に覗いているから新しいものが入っているとも思えず)WORLDやLATINのコーナーを散策していて偶然目にとまったのがコレ! なかなかいいジャケットでしょ。 レモンイエローのベース色と黒人の姿のジャケットをしばらくの間試聴機の前で見ていた。 聴いてみた。 直感が当たった。 TOWERのPOPを読むとデビッド・ボウイの楽曲をポル語でギター一本で弾き語りしているというのが分かった。 その瞬間に買いが決まった。 デビッド・ボウイは中学時代の同級生がレコード集めていたのを横目で見ていたくらいで、これまでの46年間の中で一度も音楽的接点のないアーティスト(私ほとんどロックを知りません。)だけれども、いい曲作ってますね。 SEU JORGEも勉強不足のため初めて聴いたブラジルのアーティスト。 リアルブラジルを代表するミュージシャンのようで2005年には日本へ来日、広島もクアトロでライブがあったらしい。 あとで調べてみて旧作のジャケは見たことがあった。 SEU JORGEのギターと唄はボサノバやサンバのリズムを多用しているが、60年代のボサノバの雰囲気はない。 そこには、リアルなブラジルの姿が投影されているように思えてならない。 今のブラジルに日常的な意味でボサノバはない。 ブラジルもロックやヒップホップ、アシェーミュージックがラジオをつけると流れていてその辺はアメリカや日本と同じ。 それでも、ブラジルのミュージシャンの音楽にはサウダ-ジがあるのです。 数年前から日本ではカフェミュージックとか何とかいってボサノバを今風な味付けでリニュアルしてプロデュースする企画が流行っていて様々なCDがリリースされていますが、私どうもダメなんです。 例の加工臭が・・・ その点、このSEU JORHEの作品は数倍、ボサノバやサンバの本質を伝えている気がしてならない。 ボサノバは決してデパートの音楽ではないのである。 2005年作品。 SEU JORGE(VO,G) -----------  年末に見つけたイギリスのボーカリストSIOBHAN PETTITによるバート・バカラック集。 「WHAT THE WORLDS NEEDS NOW IS LOVE」「A HOUSE IS NOT A HOME」「THE LOOK OF LOVE」「CLOSE TO YOU」「I SAY A LITTLE PRAYER」「WALK ON BY」「WIVES & LOVERS」お馴染みの名曲がずらり。 ジャケットの顔もいいではないか! この時点で買うっきゃないでしょう! ジャズの作曲家以外では、本も出版されているけれど、私もルグラン、ジョビン、バカラックで決まりだと思う。 このアルバムは彼女の3作目の作品で、過去の作品もスタンダードナンバーや自作にエルビス・コステロやバカラックの曲を加えたものだった様。 冬の晴れ渡った柔らかな日差しの様な、きりっとしているのだけれどどことなく温もりを感じさせる爽やか清涼系の声質はバカラックのようなポップナンバーにうってつけだと思う。 今、「恋の面影」が流れているけど、この曲を聴くと映画に出演していたウルシュラ・アンドリュースの艶やかな姿を思い出す。 バイオを見るとクリントン元大統領や007のロジャー・ムーア(ここでつながりましたね!)も彼女のファンだというではないか。 そんな彼女もジャズだけの仕事ではなかなか飯がくえないらしく、ヴァン・モリソンのバックボーカルやエンゲルベルト・フンパーディンク、マイケル・ヴォルトンと仕事をしたりしているようだ。 フィリピンで人気が出てきているようで今後に期待したいボーカリストです。 先物買いのボーカルファンのかたには新春お勧め第1号です。 -----------  このピアノトリオ作品は本当だったたら昨年入荷しているはずだったのだけれども、遅れ遅れになってようやく昨日入荷したもの。 JOEL HOLMESは1982年12月生まれというからこの作品をリリースして時点では22才の若い黒人ピアニスト。 一曲目からぶっとばしてくれます。 マッコイ系のめまぐるしく鍵盤上を駆け巡る指裁きは、最近の若手ピアニストではあまり聴いた記憶がないのだけれど、なかなか大したもんです。 スピード感だけでなく、地にしっかりと足をついた力強さ、安定感もあるので危なげがない。 そして、若い黒人ならではのバネの力を感じさせる。 はちきれんばかりの柔軟性に富んだゴムマリのような筋肉から生み出される瞬発力。 これは、われわれ日本人や白人が束になってかかっても勝てないところだろう。 運動能力のすばらしさだけではない。 4曲目の暗い海底の奥底に沈鬱するような深い叙情性を、繊細に描き出す表現力。 「BODY AND SOUL」を4度演奏しているが、別テイクというものではなくてすべて違う内容であり、そのバリエーション豊かな表現能力にも驚かされ、技術面での力量がうかがわれる。 オリジナルも良いのですよ。 1曲目「HOLYSPIRIT」4曲目「DIVINE REVELATION」6曲目「ONE LIFE TO LIVE」 7曲目「MY SUNSHINE」。 欧州ピアノトリオもいいけど、一年のスタートにあたりこういうフレッシュな黒人正統派ピアノトリオを聴くのもオツなものだと思うのですが如何なものでしょう? エリック・バード・トリオのファンの方にはきっと気に入っていただけると思います。 ----------- 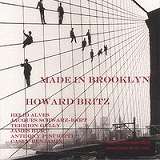 2005年にリリースされたベーシストHOWARD BRITZをとりまくブルックリンとその周辺で活躍する音楽仲間のセッションがコンパイルされた作品。 HELIO ALVISやJACQUES SCHWARZ-BARTの名前が目に付く。 ジャケットのデザインワークがBLUENOTEの10インチ盤のようで興味がわく。 1~3曲目までは、HELIOとSCHWARZ-BARTが加わったカルテット録音。 SCHWARRZ-BARTは最近ではアリ・ホ-ニッグのスモールでのライブがシューティングされたDVDで素晴らしいプレイを展開していたけど、この作品でも快調ぶりを発揮。演奏していると結構熱くなってくるのか、ブロウしたフレーズも端々に聴けてブルックリン派のテナー奏者では珍しい存在かもしれない。 もちろん、激情型のプレイではなくて巧みにコントロールされたものなのだが・・・。 HELIO ALVESの軽やかで活気のある鍵盤使いと良いコントラストを描いている。 NYの「スモールズ」や「55 Bar」では夜毎深夜のそれも遅い時間にこんな音楽が演奏されているのだろうなぁ。 意識的に新しいこと、革新的なことをやろうとしているのでもなく、かといって過去のジャズをリバイバルするのでもない。こういった現場やリハーサルから自然発生的に生まれてきた等身大のサウンドをセッションのたびに新しいアイディアを注入して膨らませていくのが彼らのやり方だろう。 そんなNYの現場でなっているサウンドがリアルに伝わってくるサウンドだと思う。 リーダーについて触れなかったけど、ソリッドなベースワークで音楽の土台をしっかりキープし全体のサウンドを統括する根っからのベースプレイヤータイプのミュージシャン。派手さはないけど、こういうプレイヤーが現場では一番重宝され尊敬される存在なのだと思う。 メンバーはHOWARD BRITZ(B)HELIO ALVES(P)JACQUES SCHWARTZ-BART(TS)ANTHONY PINCIOTTI8DS)TERREON GULLY(DS)JAMES HURT(P)CASEY BENJAMIN(AS) 2005年作品 -----------  NYのギタリストBOB GALLOが2005年に自費制作で発表したデビュー作。 いままで、ショービジネスやスタジオワーク、テレビ局やサウンドトラックの仕事をメインにしてきたらしく、この作品が本格的なジャズレコーディングの第1作目のようだ。 とにかくオープニングの「WAKE-UP CALL」を聴いてみてほしい。 ようやく眠れる未完の大器が目を覚ましたのだ。 ジャック・ウィルキンスやルイス・スチュアートばりの素早くスムースなフィンガリングによるやる気のみなぎったプレイにこのセッションに参加したALEX SIPIAGINはいつにましてトランペットをブロウするわ、GENE JACKSONはドラムをこれでもかとしばきあげる様にミュージシャンの興奮が見て取れる。 スタジオでハプニングが起こっているのだ! 集ったミュージシャンが、予想以上の素晴らしいBOB GALLOの凄いプレイを目の当たりにしてインスパイアされ、全員が乗りに乗ったプレイを展開していると言ったら良いだろうか。セッション自体が良い方へ向かい、音楽の魔法が起こったいい例ではないか? こうなると、そこは百戦錬磨の名うてが集っているだけにこのアルバムの成功は約束されたようなもの。 最近のギタリストはカート・ローゼンウィンクルやベン・モンダーなような寄り道系のプレイを得意とするサウンド志向の奏者が注目を浴びているけど、既に中堅デイブ・ストライカーやCRISSCROSSからソロアルバムを連発しているジョナサン・クレイスバーグなどストレートなプレイ志向のミュージシャンも頑張っている。 ピアノトリオ全盛(日本だけの現象?)の今の時代ギター界もこんな風に有能な人材がどんどん出てきてシーンを盛り上げてくれることを願う。 ギターファンを自称する方には是非聴いてもらいたい1作です。 メンバーはBOB GALLO(G)ALEX SIPIAGIN(TP)MISHA TSIGANOV8P)BORIS KOZLOV(B)GENE JACKSON(DS) 2005年作品 BROOKLYN, NY -----------  ボルチモア生まれで現在ワシントンエリアで活躍するTOM BALDWINが2002年にリリースしたデビュー作品。 1995年に開催されたセロニアス・モンク・コンペティション(ベースの年)で見事第2位を獲得してほどなので、腕前は保証つき。 今までにEric Alexander, Gene Bertoncini, Stanley Cowell, George Garzone, Fred Hersch, Brian Lynch, Harold Mabern, James Moody, James Williams,などと共演した経験がある。 この作品はピアニストにGEORGE COLLIGANを迎えていることが大きなポイントになっていて、リーダー作では時々頭脳明晰のためか少々頭でっかちな観念的プレイに走りすぎるきらいののあるコリガンも、ここでは適度にリラックスした素晴らしいプレイを展開している。 もともとテクニックのある人なので、平常心でリーダー作にも望めばもっと良い作品が作れると思うのだけど、どうしても気負いが先立ってしまうのだろうか? もっとも、新しいことにトライアルするチャレンジ精神は必要だし、その辺のさじ加減がリスナーとアーティストの間には常につきまとう問題であるのは確かです。 聴く側から言わせてもらえば、どれだけ楽しませてもらえるか、再度の試聴に耐えるか、長年に渡って聴けるかという事は間違いなく重要な問題だから。 最近のウェイン・ショーターのアルバムにも当てはまるかもしれない。 間違いなく素晴らしいのだけど高尚過ぎて日常的聴きには適さない。 まあ、盆と正月にしか聴かないというか聴けない(実際ほとんどの熱心なジャズファンは時間的物理的問題からそうだろう。)アルバムがあっても全然かまわないのですけどね。 ギル・メレやトリスターノ(これはいそうな気がする)をほとんど毎日のように聴く人がいないように・・・ なんか脱線してしまったけど、一曲を除き全曲オリジナルの純正ジャズ作品です。 サックスのCHRIS BACASも個性という点では少々物足りない点はありものの、まずは合格点のプレイ。 FSNT,CRISSCROSS,最近のSTTEPLCHASEあたりを追っかけている方にはお奨めの一枚です。もちろんコリガンファンの方にも。 メンバーはTOM BALDWIN(B)CHRIS BACAS(TS,SS)GEORGE COLLIGAN(P)HOWARD CURTIS(DS) 録音は2001年4月18日 NY -----------  トロント生まれのピアニスト、JOHN MACKAYが2002年にリリースしたピアノトリオ作品。題名通り、ウェイン・ショーターとハービー・ハンコックの楽曲にフォーカスした作品で、二人のミュージシャンのファンには関心をひく作品ではないだろうか? 3曲目で「BLACK NILE」も演っているぞ! 最近ようやく出回りだした「ジェラルド・ヘイゲン・トリオ」もこのブラックナイルを取り上げていたけど、それに勝るとも劣らぬ仕上がり。 3分21秒というコンパクトな時間で一気呵成に弾ききったところに勝因があるのかも知れない。 4曲目ではショーターの隠れバラード名曲「LADY DAY」なんてマニアックな曲を取り上げてくれているところも憎いではないか。 ピアノトリオ(シンセの使用あり)でウェザーの「MYSTERIOUS TRAVELLER」を取り下げたのはこのJOHN MACKAYが初めてじゃなかろうか? 曲によってはエレベが使用されていて全体として聞いた場合、リズムセクションの物足りなさは残るものの、決して足を引っ張るほどひどくはないので、うるさ型のジャズファンの方にも十分満足してもらえる内容だと思います。 ラスト2曲はハンコックの「DOLPHIN DANCE」と「TELL ME A BEDTIME STORY」。 私と同世代かすこし上の世代のかたには、このあたりの曲は涙ものの選曲でしょう。 ショーター、ハンコックフリークの方は是非聴いてみてください。 メンバーはJOHN MACKAY(P,SYNTH)STEVE ZERLIN(B,EL-B)ALAN HALL(DS) 2002年作品 ------------  ピアノトリオらしいピアノトリオってきっとこんな具合のトリオを最も言うんだろうなぁ。 一曲目のハンク・モブレーの「FUNK IN DEEP FREEZE」を聴いての素直な感想。 楽曲の魅力を最大限に引き出して見事に響かせるテクニックはこの一曲目で感じられる。 よく、ピアノの習い始めに、「手の形はこう」と卵を手のひらでつつむ形を教わらなかったでしょうか? MAX LEAKEのピアノタッチにはそんな基礎の基礎というか、ピアノを弾くときの最も基本となるところが感じられるのです。(実際のところはどうなのか分かりませんが・・・) ウィントン・ケリーばりの弾むようなグルーブ感やボビー・ティモンズのブロックコードをうまく使ったファンキー感覚溢れたアクション技に耳を奪われる。 フレッド・ハーシュ「HEART SONG」や「A TIME FOR LOVE」では欧州ピアノトリオに負けない叙情感溢れるロマンティコが注入されているし、4曲目「JUST YOU,JUST ME」ではピート・ジョリー、ルー・レヴィー、サイ・コールマンなんかの洒落た感覚いっぱいの古き良きアメリカ白人ピアニズムが満喫できるといった仕掛け。 もちろん現代のピアニストであるから、エバンス以降の現代モダンジャズピアノのマナーを完全にマスターしているのは言うまでもない。 選曲の多彩さも特筆できる。 ジョニ・ミッチェル「BOTH SIDE NOW」サド・ジョーンズ「THREE AND ONE」ショーター「VIRGO」「HARLEQUIN」ルイス・ボンファ「MENINA FLOR」ケニー・カークランド「DIENDA」バド・パウエル「CRAZEOLOGY」 バラエティーに富んだ楽曲を前にして適材適所的に自身のピアノテクニックを当てはめて解釈する能力は、まさにプロ中のプロ。 うるさがたからこんな声が飛んできそうである。 だったら、このMAX LEAKEの個性はどこにあるんだと。 ピアノは元来小さなオーケストラと言われるなんでもできる最も表現能力の高い楽器。その特性を最大限に生かしきって何でもできるピアニストがLEAKEじゃないかな。 こんなピアニストが一人くらいいてもいいんではないでしょうか。 決して器用貧乏ではない、是非聴いてもらいたいピアニストです。 ふた通りのリズムセクションとの相性もバッチリでうるさがたのピアノトリオファンにも納得いただける内容だと思う。 メンバーはMAX LEAKE(P)DWAYNE DOLPHIN(B)PAUL THOMSON(DS)GREG HUMPHRIES(B)THOM WENDT(DS) 録音は2004年5月3,24,27日 PITTSBURGH,PA ----------  いやぁー、綺麗な「おねいさん」が春風に乗って帰ってきてくれました。 こいつは春から縁起がいいやぁー! 前作は2001年のリリースだったので、実に4年ぶりになるのですね。 その素晴らしいジャケットが評判を呼び、ネット上でも随分話題となりJOAN BENDERのことを「おねいさん」と呼称するのが流行っていたはず。 その相変わらずの美しさはそのままに、歌もうまくなったのではないか。 今回もスタンダード、ジャズマンオリジナル、ボサノバ、ラテンの名曲を絶妙な配分でラインナップして、楽しませてくれます。 おまけに新作はミュージシャンが凄いんです。 デビッド・ヘイゼルタインのピアノ、ポール・ギルのベース、グラント・スチュアートのサックス、NYのトップミュージシャンをバックを担当。 「SO DANCO SANBA」「O GRANDE AMOR」「BODY AND SOUL」「SUUNY」「OVER THE RAINBOW」「ALL BLUES」「GOD BLESS THE CHILD」「FRENISI」「TENDERLY」「BOTH SIDES NOW」「S'WONDERFUL」「INVITATION」「BUT BEAUTIFUL」など名曲を可憐に軽やかに、時にはセクシーで悩ましげに、またある時は舌足らずな可愛らしい表現で楽しませてくれます。 こういう作品はとやかく言ってもはじまりません。 ジャケットをためつがめつしつつ、ブランデーでも舐めながら鑑賞するのが正しいジャズファンのあり方でしょう。 メンバーはJOAN BENDER(VO)DAVID HAZELTINE(P)GRANT STEWART(SAX)PAUL GILL(B)JOE STRASSER(DS)PAUL MYERS(G) 録音は2005年 NYC -----------  バートとラリーのDALTON BROTHERSは、1960年代ウィスコンシンの自宅のリビングルームでラムゼイ・ルイスやオスカー・ピーターソンのコピーをすることから演奏の第一歩を踏み出した。 音楽的にはその後袂を分かち、それぞれの道を一時進んだが、一緒に活動する思いが日増しに強くなって、2002年の夏、「GREAT JAZZ FESTIVAL」でドラマーのRICH MACDONALDを加えて正式に結成されたそうです。 このトリオに夜の雰囲気はない。 そう、ジャケットの絵のような、休日にピクニックに訪れて小川のほとりでランチを広げながら聴く感じなのである。 川のせせらぎや鳥の鳴き声、野山の景観を眺め、花を愛でる。 そんな野外で太陽の光を浴びながら聴くサンデイ・ブランチ・ジャズといった趣がある。 そうそう、「真夏の夜のジャズ」のカットシーンで海辺でウィンドサーフィンやヨット遊びに興じているシーンがあるでしょ。 きらきらと光る海の風景。 ちょうどあんな感じといったら良いでしょうか? 演奏はもちろん本格派、スピーカーの前に陣取って清聴するのもまったく問題ありません。 コンコードやキュアロスキューロあたりのオーソドックスでスインギーな白人ピアノトリオジャズをお好みの方にはきっと気に入っていただけると思います。 メンバーはLARRY DALTON(B)RICH MACDONALD(DS)BERT DALTON(P) 録音は2004年5月14-15日 ------------ 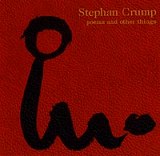 クリス・チークの最新アルバムがようやく入荷したようです。 私はまだ未入手なのですが、funky_alligatorさんのブログ電車で轟(GO)!によると、マニアックなナンバー(Eral Bosticで有名なFlamingo。Ellingtonナンバーで有名とは言えないLow Key Lightly。Tommy Dorseyで有名なRimsky-KorsakovのSong Of India。Henry ManciniのThe Sweetheart Tree)をパワー全開で吹ききっているようで、聴くのが楽しみです。 そういえば、販売用に仕入れた作品のなかにクリス・チークが参加しているものがあったなぁと思い出し、早速聴いてみようとCDトレイのなかに入れてみた。 アレレッーー!音が飛ぶ。もう一度入れなおしても駄目。もう一台のプレイヤーに入れてみるが読み取りもしない。 盤自体に傷もないし、ゆがみもない。 何故、かからないのか分からない(他のプレイヤーならかかる可能性もあり?)のだけど、千枚に一枚くらいの確率で時々こういうケースがあるので諦めた。 そうすると、余計音源を聴きたくなるのが人情で、駄目もとでパソコンのトレイに入れてみた。 ちゃんとかかるじゃん!!! STEPHAN CRUMPの楽曲はゆったりしたテンポの内省的なものが多いのですが、ロバータ・ピケットの雪の結晶に光があたったような、きらきらと舞い降りるような美しく思索的なピアノと、チークの倍音成分をいっぱい含んだふくよかなサックスの音はよくあっている。 メロディーが抽象度3割、内省度3割、旋律度3割といった配分でこの辺もブルックリンサウンド近辺の音を好む方には丁度いい塩梅なのではないか? メンバーはCHRIS CHEEK(TS,SS)ROBERTA PIKET(P)ROB GARCIA(DS)STEPHAN CRUMP(B) 録音は1997年1月29,30日 ------------  ブラジルの名ピアニストが2005年にリリースした最新ピアノトリオ作品で、4曲にスペシャルゲストとして、MAURO SENISE,JOYCE,IVAN LINS,WANDA SAを迎えた豪華なつくり。 選曲もブラジルの名曲をずらっと並べ、私のようなブラジル音楽大好き人間のジャズファン(変な言い方?)にとって、申し分ないつくりとなっています。 アリ・バローゾの「PRA MCHUCAR MEU CORACAO」で幕をあける。 私はこの曲を中村善郎さんのCDではじめて知ったのですが、実にブラジルらしい雰囲気がする美曲で、GILSON PERANZZETTAは力の抜け切ったナチュラルな表現で演奏、それでいて音の立ち上がりが際立っていて煌びやかなのです。 ボンファの有名曲「カーニバルの朝」にはサックス奏者のMAURO SENISEが参加。 通常のジャズセッションで使われるボッサリズムはここでは使われていない。 他の曲にもいえるのだけど、通常ブラジルのこの作品で取り上げられているような有名曲を日本を含め他国のミュージシャンが演奏する場合、ほとんどの場合決まりきったボッサリズムが使われていると思うのですが、ブラジルのジャズミュージシャンがプレイする時、リズム処理がもっと柔軟で幅がある点が面白い。 5曲目ではJOYCEの魅力的な声が聴ける。いつ聴いても変わらない深く情緒にあふれた声はここでも健在だ。9曲目にはIVAN LINS,12曲目にはWANDA SAが参加している豪華さで、花を添えている。 古いラテンナンバー「TICO TICO」やジョニー・アルフの「若者の歌」を演ってくれているのもうれしい限り。 PERANZZETTAのピアノは一般的なジャズの語法から見れば、決してテクニシャンとは言えないのかもしれないけど、野に咲く一輪のきれいな花に太陽の光が燦燦と降り注いでいるような、自然で素朴でそれでいて芯の強い心を豊かにしてくれる風のように軽やかなピアノだと思う。 本場のブラジリアンピアノが満喫できる一枚としてお奨めしたい。 メンバーはGILSON PERANZZETTA(P)PAULO RUSSO(B)JOAO CORTEZ(DS)+GUESTS 2005年作品 ------------  去年の夏、BRAMBUSのROLF HASLER「WALKING THREE」を聴いたとき、リーダーより感心して耳をそばだてたのがこのJEROME DE CARLIだった。 このブログにも確か、ピアノトリオで聴きたいことを書き記したと思うのですが、 少ししていいタイミングで同じくスイスのレーベル、JAZZ ELITEから「WHO CARES」が発売された。 HASLER盤を聴いたときの好印象が、一曲目バリーハリスの「BISH BASH BOSH」を聴いたとたん、確信に変わった。 素晴らしいピアニストが醸しだす隠しとおせないジャズの芳しい気品、輝き、リラクゼーション、スピリッツ、最高の賛辞を捧げてもいいのではないかと思わせるぐらい素晴らしい演奏が収められていると言っても良いのではないかと思う。 この作品、ちょつと良いくらいではなく、相当良い部類にランクされる作品なのではないかと思う。 たぶん、長い間に渡って鑑賞するごとに愛着が増すスルメ盤だと思うのだ。 たぶん、経験から言って間違いない。 ピアノトリオファンはもとより、ジャズファンのかたは入手しておいたほうが良い一枚だと、思います。 この作品で私の中でJEROME DE CARLIの占める位置が俄然大きくなって、調べてみると過去にもこのメンバーでトリオ作品をリリースしていることが分かった。 ギリシャ、アテネ録音のようだ 「Jerome De Carli/The Way I Like It」 Flanagan (De Carli) The way I like it (De Carli) Transition (Antoniou) One for Mulgrew (De Carli) La Habana (De Carli) March on June (De Carli) Stella (De Carli) 11th Street West (De Carli) Blues ’n’ Groove (De Carli) Without a Song (Youmans/Rose/Elisen) Recorded 7. & 8. July, 1998 もう1枚は1999年チューリッヒのジャズクラブでのライブ録音で 「Jazz Pan」 Have you met Miss Jones (Rodger&Hart) Beautiful Love (Victor Young) Recordame (Joe Henderson) Straight no chaser (Thelonious Monk) C Jam Blues *(Duke Ellington) Fee fi fo fum (Wayne Shorter) On green Dolphin street (B.Kaper) In a sentimental mood (Duke Ellington) Recorded Live at Free Friday Carnival Club 4. June 1999, Zürich, Switzerland 滅茶苦茶聴いてみたいです。 今からJEROMEにコンタクトとってみようと思います。 -----------  イギリスのボーカリストSALLY DOHERTYの2005年作品で、スタンダードやサンバ、ボサノバ、ボレロの名曲の数々を英語、ポルトガル語、スペイン語を駆使して謳いあげるという内容の作品。 イギリスではクレオ レーンのオープニングアクト(悪く言ったら前座だけど)や重鎮ピーターキング、アランバルネと共演もしているらしい。 ひんやりした冷気が運ばれるようなウィスパー系ボイスがなかなか魅力的で、ラテンアレンジの曲とポルトガル語やスペイン語による歌唱がよくあっている。 「WHAT A DEFFERENCE A DAY MAKES」、ダイナ・ワシントンの名唄が未だに耳について離れないのだけど、こういうバージョンもいいねぇ! ダイナの唄がブルースの心情に溢れた人間の感情の発露をストレートにぶちまけたものだとしたら、サリーの唄は洗練されたスタイルで、さりげない表現は都会的なスマートさを感じさせる。 真夜中の気だるい淀んだ空気の場末の酒場と日のあたる明るいフレンチカフェの午前11時の風景との違いだろうか? まったく違う曲に聴こえるけど、これも良いです。 アリ・バローゾの「E LUXO SO」もいいし、「BESAME MUCHO」もこの人が唄うと不思議とベタな感じがせずに、爽やかさを感じさせる。 ダイナの唄がバーボンストレートだとすれば、サリーの唄はミントリキュールソーダ割りライム添えみたいな感じかな。 すっきり爽やかなのである。それでいて、唄のメッセージは充分、伝わってくる。 バックのピアノトリオも良いサポートをしている。 今後も期待したいボーカリストだと思う。 メンバーはSALLY DOHERTY(VO)PIETRO TUCCI(P)COLLIN ELLIOT(B)CAROLINE BOADEN(DS) 録音は2005年3月25日、5月17日 ------------  年明けに注文したCDが今日オーストラリアから届いた。 CHINDAMOからもうすぐ新作をリリースするというメールを去年の秋にもらっていたのだけど、それが本作ともう一枚のウンブリアジャズ祭でのソロ作品のことだったんだ。 GRAEME LYALLの名前は勉強不足のため、初めて聞く名前のサックス奏者だけど、60年代のコニッツの音色を持つ素晴らしいサックス奏者だと思う。 メルボルンとシドニーを行ったり来たりしながら、ジャズのライブ活動以外に、音楽教育の仕事、オーケストラでの活動、スタジオワーク、テレビ局の仕事など様々なミュージックビジネスによって培われた経験はベテランならではの風格を感じさせる。 JOE CHIDAMOのトリオ以外の作品は初めて聴いたのだけど、スムースでジャージーなキーワークは安定度抜群で、すでに巨匠の風格を漂わせている。 今まで澤野から日本でリリースされている印象に比べて、本作ではグルービー度が増しているというか、なんてことのないフレーズにこの人ならではのファンキー節が盛り込まれていて、これは新たな発見だった。 デュオやスローナンバーではいつものように、輝かしい粒立ちのよい美しいピアノも健在で、ワンホーン作品といってもふんだんにチンダモのソロが楽しめるのでご心配なく。 あえて苦言を呈するならば、少々スノッブ性を強調しすぎたかなという点。 LYALLとCHINDAMOのオリジナル14曲で構成されているので、チェンジオブペースで、スタンダードやジャズメンオリジナルを2,3曲づつ挿入したほうがもっと聴きやすくなったと思う。 10,11曲目ではチンダモのアコーディオンの演奏が聴ける。 これは、良かったです! メンバーはJOE CHINDAMO(P,ACCORDION)GRAEME LYALL(AS,SS)SAM ANNING(B)BEN VANDERWAL(DS) 録音は2004年6月9日 ----------- ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|
||